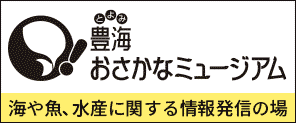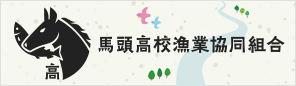水産振興事業
(一財)東京水産振興会は1967年以来、水産に関するさまざまな課題をテーマとして、講演会の開催や「水産振興」の発行、調査研究事業などの水産振興事業を行い、印刷物の刊行・配布などによりそれらの成果を公表してきました。2019年度からは、「供給者(生産・流通)と消費者(都民・国民)の双方の視点に立った水産業の振興」を水産振興事業の目標に掲げ、下記Ⅰ〜Ⅴの5つのテーマを設定して各種の事業を推進しています。また、これまでに実施した事業の刊行物情報および現在実施している事業の詳細情報などを幅広く発信するため、下記のとおり事業別の専用ウェブサイトを開設していますので、ぜひご覧ください。
I. 持続的な資源利用
水産資源の有効利用のために、流通業者などを交えた利用者からの観点での議論を促し、資源利用に対する共通の認識と理解を醸成することを目的としてさまざまな団体・機関と連携し、調査研究の実施、講演会の開催やウェブサイトでの情報発信などを行っています。1. わが国周辺の水産資源と漁業の構造変化に関する調査の実施
(一社)全国水産技術協会へ委託し、沿岸漁業を主体に近年の気候や水産資源の変動に対応した、水産物消費の構造変化等を分析し、沿岸漁業の水産物供給における役割とあり方について展望します。2. 漁村地域女性グループ活動支援
漁村地域の女性グループによる活動を活性化するために必要な要素などを明らかにするため、一般社団法人うみ・ひと・くらしネットワークに委託して地域漁業や漁村コミュニティへの支援を実施しています。ウェブサイト「漁村の活動応援サイト」では研究成果および漁村に暮らす人々の活動事例や商品販売などの情報を紹介していました。2024年度より「水産振興ONLINE」(下記Ⅴ)内の「水産振興コラム」で情報発信しています。
3. 水産振興ONLINE、ワークショップ、講演会等による発信
「水産振興ONLINE」(下記Ⅴ)にて、水産や資源に関する「水産振興誌」および「水産振興コラム」を公開しています。また、関係団体と連携してワークショップや講演会を開催しています。
II. 魚の消費拡大
水産物の供給者と一般消費者との繋がりを強化できるような仕組みづくりの提案や情報発信を行なうことで水産物のイメージアップと消費の拡大を目指した事業を以下のとおり実施しています。1. 豊洲市場を中心とした水産物マーケットに関する調査研究
水産物マーケットがどのように変化しているか、その動向を把握し今後を展望することにより、市場をはじめとする水産業関係者のビジネスモデル構築や経営戦略を考えるに資する基礎資料を提供します。2. 水産振興ONLINE、ワークショップ、講演会等による発信
卸売市場を中心として、供給動向(生産、輸出入)ならびに消費動向を見据えた水産物の消費拡大を目指し、「水産振興ONLINE」(下記Ⅴ)、ワークショップ、講演会等で情報発信を行っています。III. 魚の棲む環境と人との関わり
東京湾を中心とした水棲生物の生息環境に関する調査や小学校等での環境教室、地域での啓発活動を進め、生き物が生息できる場づくりについて考え、人と生き物にやさしい地域づくりを目指します。1. 運河域を主とした生き物にやさしい環境づくり(朝潮運河いきものルネサンス)
(1)生物調査東京湾のマハゼおよび豊海町周辺の朝潮運河に生息する生き物について、生息環境の把握や生息場所の保全などを目的として「江戸前ハゼ復活プロジェクト・マハゼの棲み処調査」および「簡易かご調査」を行い、生き物に適した場づくりを考えます
(2)環境教育について
豊海水産埠頭に隣接した豊海小学校を中心に、「朝潮運河を子どもたちの里海に」を目標として運河と地域学習をカリキュラム化し、広義の海洋教育を目指しています。
(3)地域との連携
行政・学校ならびに運河ルネサンス協議会等、地域活動を担う人々と協働で生き物と共存する地域づくりを行っています。
2. 人と生き物にやさしい川づくり
河川管理者(国交省、都道府県)と水産関係者(水産庁、内水面漁連、都道府県水産課)との協働による川づくりを実施し、魚や水辺の生き物に適した河川の実現と人と生き物が共存する川づくりを目指しています。ウェブサイト「馬頭高校漁業協同組合」では、過去の研究成果や各地の取り組み事例などを紹介しています。3. 水産振興ONLINE、ワークショップ、講演会等による発信
「水産振興ONLINE」(下記Ⅴ)にて、環境に関する「水産振興誌」および「水産振興コラム」を公開しています。IV. 魚と健康づくり
魚食の良さについて健康・食生活・環境などさまざまな側面から研究を行い、その成果を踏まえた「さかな丸ごと食育」を以下のとおり実施しています。研究成果や教材、活動実践などの詳細はウェブサイト「さかな丸ごと食育」をご覧ください。1. 「さかな丸ごと食育」活動の実践
NPO法人食生態学実践フォーラムと連携し、学習教材「さかな丸ごと探検ノート」を使用した食育学習会を全国で開催しています。また、「さかな丸ごと食育」学習会を実施する養成講師の認定を行い、研修会等による継続的なフォローアップにも取り組んでいます。(一財)東京水産振興会でも、上記食育学習会の一環として「豊海おさかなミュージアム食育セミナー」や、中央区との連携講座を実施しています。ウェブサイト「豊海おさかなミュージアム」内の「マッハBlog」ページでは「食育セミナー」の紹介記事を掲載しています。
2024年度からは、東京都と共同で「東京魚食普及員派遣事業」を開始し、都内小中学校での出前授業を行っています。
2. 絵本「まるまる みんな いただきます!〜かわも うみも やまも さかなも〜」を主教材とした活動
足立己幸女子栄養大学名誉教授をリーダーとする研究グループに「さかな・乳幼児の食事・食を営む力や生きる力の形成・環境のかかわり」に関する食生態学的研究を委託し、幼児発信型絵本教材『まるまる みんな いただきます!〜かわも うみも やまも さかなも〜』を制作しました。現在は教材の普及を行っています。V. 情報発信
「水産振興ONLINE」を中心に、ネットを活用したコミュニケーションなどについて積極的に推進し、資源・漁業ならびに消費者とのつなぎ役である卸売市場を中心とした流通・小売の動向を発信しています。また、豊海水産埠頭と地域との交流場所として豊海おさかなミュージアムを運営しています。1. 水産振興ONLINE
「水産振興ONLINE」では、水産に関するさまざまな内容を情報発信しています。(1)水産振興誌:水産に関する寄稿および講演会などの記録
(2)水産振興コラム:連載を中心としたコラム
(3)資料館:(一財)東京水産振興会がこれまでに実施してきた各種事業の紹介および刊行物情報